はじめに
投資で勝ち抜ぬくためには、知っておくべき重要な数字があります。
SNSや広告にあふれる“うますぎる話”や、不安を煽るニュースに振り回されることなく、
資産を着実に増やすには「正しい数字を知り、それをどう使うか」がカギになります。
今回は7%・10%・20%・30%という投資家が知っておくべき数字を、
その「意味」と「実践での使い方」に絞って紹介します。
■ 投資の“下落率”は「最高値からどれだけ下がったか」で見る
まず大前提として、投資でいう“下落率”は、その時点での最高値から、いま何%下がっているかで計算します。
細かいルールは気にしなくても大丈夫です。
「今の株価が直近で一番高かった時から何%下がっているか」を知っておいてください。
7%──現実の“平均リターン”、幻想にダマされるな
- 年7%前後が、世界株・米国株の長期平均リターン。
- 投資の神様、ウォーレン・バフェットも「年7~8%の複利が最強」と断言。
- この数字を知っておけば、1年で倍になるなどの怪しい投資話に騙されることはないはずです。
投資を始めてある程度勉強した人なら誰もが知っている数字だと思いますが、この数字を知っているのと知らないのとでは、投資をするうえで大きな差を生むことになると思います。
10%──最高値から10%下落、「調整局面」は日常茶飯事
- どんな好調相場でも10%くらいは普通に下がります。
- これでパニックになったら投資家失格。
- 持ち株の評価額が一時10%下がっても、「よくある波」と受け流せるようになりましょう。
投資を始めたばかりの頃は、資産がマイナスになるだけでも不安になりますよね。でも、株価は安定的に右肩上がりにはなりません。上がり下がりを繰り返しながら徐々に上がっていくものです。長期投資家なら、短期の上下を気にする必要はないですし、むしろ下がってくれた方が欲しいものが安く買えるんですよね。安く仕込んだものをじっくり寝かせて育てていく。これが長期投資です。
20%──最高値から20%下落、「弱気相場(ベアマーケット)」突入
- 株価指数が最高値から20%以上下落すると「本気の下げ」とニュースも大騒ぎ。
- ここでビビって売ると“カモ”一直線。むしろここが“勝ち組”の買い場の始まり。
暴落時に買い向かったバフェットは巨万の富を築いた。“恐怖の時に貪欲であれ”は真理。ただ、無理に買い向かう必要はありません。積立投資を継続するだけでも、後々、大きなリターンになって返ってきます。
30%──最高値から30%超の下落、“歴史的大暴落”すら想定内
- 数年に一度の危機では30%~50%下落も珍しくない。ここからが本格的な買い場。
- 大半はここで退場するが、持ち続けた人だけが後に大きく勝つ。
- 自分の“耐えられる下落率”をこの数字で点検しておくことが大切。
長期投資をしていれば、このような下落相場に直面することは何度かあると思います。このとき、狼狽売りしてしまっては長期投資の果実を得ることができません。長期投資とは、お金だけでなく、時間も投資するものです。時間を投資しない者の多くは、市場のカモになっていきます。
【体験談】──この数字をもっと早く知っていれば
投資を始めたばかりの頃はどれくらいのリターンが投資で見込めるのかが分かりませんでした。インターネットで少し調べれば出てくる情報ですが、投資初心者はどの情報が正しくて、どの情報がフェイクなのか、見分けがつけれません。
どれくらいのリターンが見込めて、どれくらいのリスクがあるものなのかをある程度把握した上で投資を始めるというのは非常に大事なことだと思います。
■ 数字をどう使うか?マネ筋道場流・実践ポイント
- 7%:現実の平均リターンを基準に、詐欺も強欲もシャットアウト
- 10%:この程度の下げは日常、気にもならないように慣れていきましょう
- 20%:暴落はバーゲンセールと心得る。20%の下落はバーゲンセールの始まり。周りの人が慌てて売り出したとき、真の投資家は買い向かい始める。
- 30%:バーゲンセールも佳境に入り、真の投資家たちはこぞって買い向かっていく。そのとき、あなたはどうしますか?無理に買い向かう必要はないですが、積立をストップしたり、狼狽売りをしたらゲームオーバーです。
バフェットの名言
株式市場が暴落して心が揺らぐときは、バフェットの名言を思い返して落ち着いて行動してください。
- 「人が恐れているときに貪欲であれ」
- 「最良の銘柄は永遠に持ち続けるものだ」
- 「市場が閉鎖されても10年保有できる株だけを買え」
まとめ|基準となる数字を知り、目安としよう。
- 下落率は「その時点の最高値から何%下がったか」だけ意識すればいい
- 「7%・10%・20%・30%」――この4つの数字を味方につけて、
焦らず、欲張らず、賢く、強く、投資の世界を渡っていきましょう。
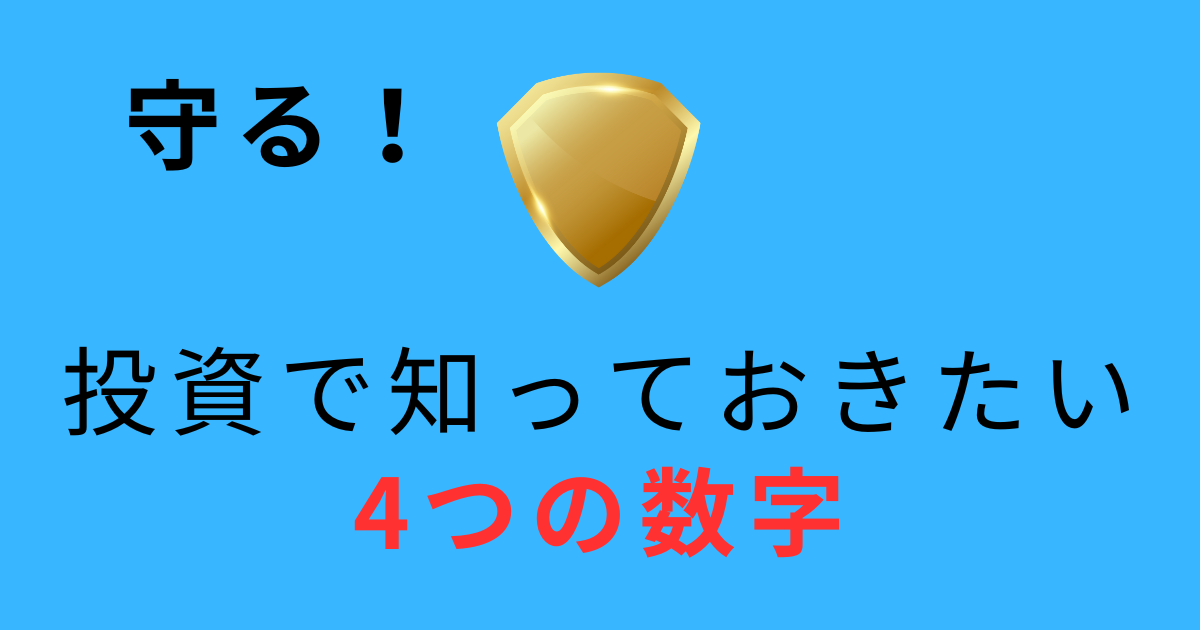
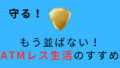
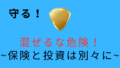
コメント